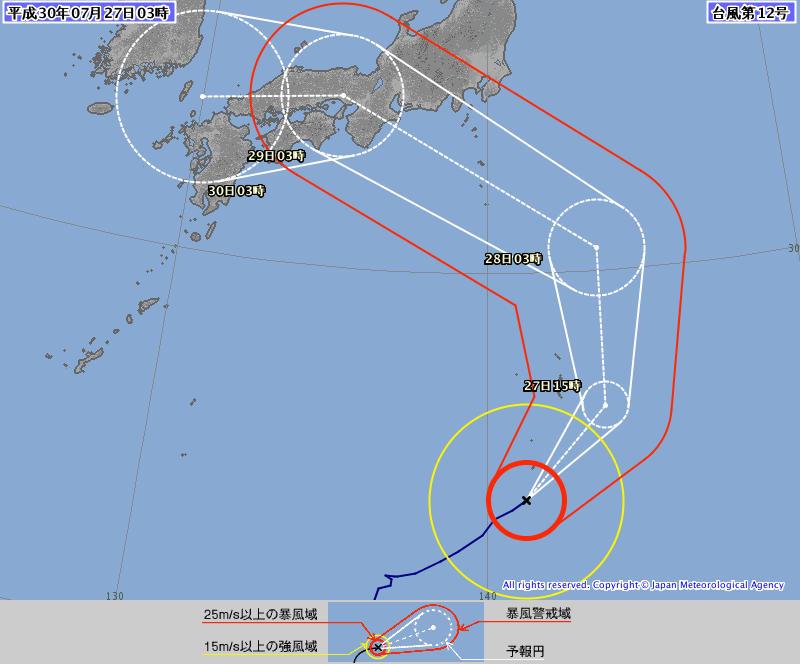平成30年(2018年)6月28日から7月8日頃にかけ、北海道や中部地方に大雨を降らせ、日本全国の広範囲にわたり長雨となりました。
台風や梅雨前線の長い時間の停滞もあり『西日本』の広い範囲で、数十年に1度しか発生しないような記録的な雨となる地域が複数あり、甚大な被害が出ました。この雨を気象庁では7月9日に『平成30年7月豪雨』と命名をしました。日本では、この豪雨について毎日報道され、日本に住んでいる方は情報が入る機会は多かったと思います。
遠方に住む方の中には『災害現場には行けないが、何かを手伝いたい』と考えている方もいるはずだと思い、この記事を書き始めました。内容は多く・長くなりましたが、今回の『平成30年7月豪雨』関連を書き出したので、情報収集の足しにして頂ければと思います。
また、過去記事『災害時、困った時の情報収集』も併せて、ご覧下さい。災害時に必要な情報全般について書いてあります。
今回紹介する内容は大まかに『豪雨による被害状況の確認・ボランティアに参加する時の注意と準備・義援金や支援金をおこなっている団体』などになります。
日本語でしか読めないホームページやSNSもありますが、基本的に英語でも読めるサイトを紹介できるように努めています。
被害状況を知る
内閣府の『防災情報のページ』で、平成30年7月豪雨についての、随時更新される『災害情報・災害対応・被災者向け情報・ボランティア向け情報』などの掲載があります。
国土交通省の『平成30年7月豪雨による被害状況等について』では『最新の被害状況を含め報告』をおこなっています。しかし、ホームページは英語で読む機能がありますが、報告書の.pdfは日本語のみです。
『総務省消防庁』の『公式 twitter』では『随時、豪雨被害の状況や消防機関等の活動を報告』をおこなっています。公式 twitterは日本語のみです。
動画サイトYoutubeで『平成30年7月豪雨』と検索した時に表示される動画です。
ボランティア参加時の注意
この記事を読んでいる方の中には『少しでも被災地の力になりたい』と考えている方も多いと思います。しかし近年、ボランティア活動も、気持ちだけで現地に行って、自分が困ったり、新たな問題を作ってしまう事があります。そうならない為にも『事前の知識と準備が必要』です。
ここでは現地に行き、ボランティア活動に『参加する前に、知っておくべき知識』と『自分が準備をする物』に分けて紹介をしたい思います。

参加前に知っておくべき知識
まず、大前提として『自分の事は、自分で責任を持つ』です。せっかく善意の気持ちを持って行動しても、被災地に迷惑をかけるくらいなら、行かない方が良いです。
具体的には
まずは『被災地の現状』を知る事です。今回の豪雨のような場合は、雨が止んでも、水が引かない地域や、通行止めになっている道路や、規制がおこなわれている地域があります。それを知らずに被災地に行くと、緊急車両や災害復旧作業の妨げになる恐れもあるので、注意が必要です。
次に『災害ボランティアセンターの開設情報』を確認する事が必要です。開設状況は『全社協 被災地支援・災害ボランティア情報』の『新着情報』から知る事ができます。このホームページは日本語のみです。
また、厚生労働省の『災害ボランティアセンターについて』では、各地方自治体の『災害ボランティアセンター』のホームページを紹介しています。
地域福祉・ボランティア情報ネットワークの『全国各地のボランティア窓口』に、全国のボランティアセンターの一覧があります。
ボランティア活動をおこなっている場所の中には『市町村内に居住している人に限定』の地域や『年齢制限』を設けている場所や、あるいは『既に募集を終了している地域などもある』ので、被災地へ行く前の確認が必要です。今回の場合、3か月近く、ボランティアが必要だと考えている地域もあるようです。焦らず、長期的になる事も考えに入れ行動をして下さい。
また、テレビなどのメディアで、被害が大きかった地域として取り上げられている場所には、ボランティアの方が多く訪れていますが『報道があまりされていない地域では、ボランティアの人数が、全く足りていない場所も多い』ようです。各ボランティアセンターやSNSの情報なども参考にしてみて下さい。
準備する物
被災地の現場に行く際に『用意』しておく必要がある物があります。先述したように『自分の事は自分で責任を持つ』という事は、現地に入ったら『被災地に迷惑をかけない』ようにする事が大切です。
具体的には
まずは、被災地の状況を確認し『作業ができる服装や持ち物』を準備する事です。
今回のような、雨による被害の場合などは、水が引き無くなると、泥が渇き『砂埃』が舞い上がり易くなります。その為、そのような状況を想定し、ボランティアに『適した服装・装備』や『備品』などの準備が必要になります。併せて、被災地までの交通手段も調べなくてはなりません。さらに、万が一の時の為に『ボランティア活動保険』への加入をお勧めします。複数日行く方は、別途、自分で『宿泊先』を確保しなければなりません。
自分自身で『災害ボランティア』自体の経験はありませんが、季節を問わずの『ボランティア活動』や『高温な場所での長時間作業』などの経験はあり、その中で、高温な部屋での過酷な作業の際、2時間おきに涼しい場所に移動し休憩を取り、毎回2リットル程の水分を摂取していましたが、それでも自分が『熱中症』になってしまい、作業ができなくなる経験もしました。
また、東日本大震災の被災地には、震災から2か月後でしたが被災地に支援の物を届けに行き、乾いた砂埃や潮が舞っている場所も経験し、帰りの新幹線の中にまで、砂埃が酷く、長時間苦しい思いもしました。過去の経験と、今回新たに調べた知識を合わせ、持ち物などの一覧を書き出しました。
ボランティア活動に参加をしようと考えている方は、下記の『適した服装・装備』や『適した物』の準備や、その理由も参考にして下さい。

適した服装・装備・理由
帽子
連日30度を超える日も多く、35度を超える地域も多いので必須です。場合によっては『ヘルメット』があると安心に繋がります。
サングラス・ゴーグル・使い捨てコンタクトレンズ
目にホコリが入らない対策と同時に、目を紫外線から守る対策も心がけたい要素です。昼間の日光の降り注ぐ、炎天下に長時間居ると、目を傷める事もあります。『UVカット付き』の物やホコリの入って来ない作りの『防塵ゴーグル』があると、砂埃などから、目を傷つける事を防げます。特にコンタクトレンズを使用している方は必須です。また、コンタクトレンズを衛生的に使う為にも『使い捨てタイプ』をお勧めします。さらに、今回の被災者の方やボランティアに参加した人などに『結膜炎の感染』が、多く確認されています。目に異物の混入を感じた時は、こすらずに、綺麗な水で洗い流すなどして下さい。
マスク
ホコリや乾いた土などを吸い込まない為に必須です。『立体型マスク』や『防塵マスク』だと効果が高くなります。乾いた土が飛ぶ事も多いので、一般的なマスクより、防塵マスクの方が良い場合もあります。また、呼吸による湿度で、濡れたり汚れるのが早い為、多めの替えがあると安心です。
厚手のゴム手袋
泥の付いた物以外でも、重い物を持つ時の滑り止めや、怪我をしそうな物から、手を守る為にも必須です。『軍手』は、これらの状況に対応できない場合もあり、十分な装備とは言えません。しかし『汗取り』として、ゴム手袋の中に利用する事には適しています。ゴム手袋の代わりに、状況によっては『皮手袋』でも代用ができます。
長袖シャツ
熱中症にならないように、気を付ける必要があります。しかし、暑くても着ていた方が良い場合が多いので必須です。半袖シャツなど、素肌が見える服装は、思わぬ傷が付く事があり、とても危険です。
長ズボン
素肌が見える服装は、不要な傷を付けかねないので必須です。
長靴
最初から履く必要のない場所も多いですが、動きやすい靴とは別に準備をします。長靴は、水や泥だけではなく、足を守る働きにも繋がります。つま先に鉄板の入った『安全靴』や、長靴で釘などを踏んで怪我をしないように『踏み抜き防止』の鉄板の入った靴などが、より効果的で安全です。靴とは別売りで『中敷きの鉄板』も売っています。災害現場には、踏むと怪我をするような、危険な物が足元に多くあるので、鉄板の入った長靴などが安心に繋がります。それぞれの靴には『軽量版』などもあります。どちらも、ホームセンターや、通販サイトで購入ができます。
上履き
避難所の中や、足元を汚さないようにしたい場所で必要になります。また、ガラスの破片や尖った木片などがあり、素足では危険な場所もあるので、あると役に立つ場面もあります。
着替え
汗を多くかいた時や、泥などで汚れた時に必要になるので必須です。帰りの服装を考える必要もあります。暑い場合・寒い場合の時も想定して準備をすると安心です。複数日の活動をおこなう場合、洗濯ができない事もあるので『多めの下着や靴下が必要』です。
適した物・理由
タオル
多めに準備をしておくと、色々な用途で利用ができるので必須です。
水分
熱中症対策には必須です。自分で持ち歩ける『水筒やペットボトルフォルダー(保温袋)』などが必要です。水筒は持ち歩く事を考えると軽い物が良いです。持ち歩く水分が『水』だと、目や手を洗う時にも利用ができます。また、複数人で行く時は、クーラーボックスに氷を多く入れ、冷たい飲み物を準備するのも良い方法です。クーラーボックスも軽量な物が便利です。
予備知識として『スポーツドリンク』と『経口補水液』の違いを紹介しておきます。
『スポーツドリンク』は、塩分よりも糖分が多めです。運動や、普段より多く体を動かし、失われたエネルギーを補うのには適しています。スポーツなどで汗いた時などには効果的な飲み物です。
『経口補水液』は、一般的なスポーツドリンクに比べると塩分は多めに作られています。下痢やおう吐などの症状がある時、脱水症状を補うには効果があります。症状が重い脱水症状の場合は、スポーツドリンクより経口補水液の方が、胃から腸に早く水分が届けられる為、症状の回復には適しています。しかし、症状が重い場合は、医師に診せたり、病院に行くなどの対応も検討をして下さい。
併せて『水だけ』を大量に摂取する危険性についても紹介します。
『水だけ』を大量に飲むと脱水症になる可能性があります。理由は、水を大量に飲むと体内の塩分濃度が低くなり、体は塩分濃度を元に戻そうと、飲んだ水を大量に尿として排出します。その結果、脱水症状を引き起こしてしまう事があります。これを『自発的脱水』といいます。その為『水分補給と同時に、塩分補給が重要』になります。
塩分
熱中症対策に、スポーツドリンクなどの他に『梅干し』や『塩飴』などが塩分補給に役立ちます。炎天下の中での作業は、想像以上に塩分が、汗と一緒に体の外に出るので、塩分補給は必須です。
簡易・応急処置セット
思わぬ怪我などの時に助かります。消毒液や絆創膏など。
ウエストポーチ
ここまで紹介した小物や、貴重品を入れる為に必須です。作業中に貴重品を持ち歩く時に便利です。背中に背負うタイプだと、汗をかき易くなるので、鞄類も小さく軽い物が作業の邪魔になりにくく便利です。
ヘッドライト
必須ではありませんが、作業は昼間でも、薄暗い場所では役に立ちます。手に持って使うタイプの懐中電灯やLEDライトは、片手がふさがる為、作業には不向きです。
レインコート
作業は晴れている時だけとは限らないので必須です。上着とズボンの上下別で使えるタイプだと、泥の多い場所などで、レインコートのズボンだけを使う事もできるので便利です。
ビニール袋
作業後、泥などで汚れた物を入れるのに必須です。多めにあると安心です。汚れた服や靴・長靴の場合は、大きい袋の用意が必要です。
ティッシュペーパー
乾いたティッシュペーパーの他に『除菌ティッシュ』などがあると、泥汚れなどを拭く時に便利です。
ボランティア活動保険
もしもの時の為に、普段使っている『保険証のコピー』や、後述しますが『ボランティア活動保険』への加入をお勧めします。
備品
ここまでは『作業時に必要』な物を紹介しましたが、他に『備品』として『状況・必要に応じ、持参すると便利な物』を紹介します。
『携帯電話・スマートフォン・充電器・予備バッテリー (充電池)・それらを繋ぐ接続コード類・パソコン・携帯ラジオ(代用:スマートフォンアプリ)・モバイルWiFi・LEDライト(懐中電灯)と予備電池・常備薬・現金・水・食料・筆記用具・身分証明書(運転免許証やパスポート)・簡易トイレ・トイレットペーパー・軍手・腕時計・風呂用具・名札入れ(ストラップタイプやクリップタイプの物など。ボランティアセンターに登録すると名札を渡される事もある為)』など。
これら、備品の多くは持って行くと便利な物を書き出していますが、自分が必要だと思う物を選んで持って行って下さい。
被災地の状況により『携帯電話やスマートフォンの電波や、WiFiが入らない』場所もあります。また、カップラーメンを持参する時は、保温効果の高い水筒を使い『お湯』を持参する必要があります。この他にも、被災地ごとに必要な道具を持参した方が良い場合もあるかも知れませんので、ボランティア活動に参加をしようと思っている被災地の状況確認を十分におこなって下さい。
なお、被災地やボランティアセンターへは、できるだけ『電話』での問い合わせはおこなわず、ホームページなどで情報を集め確認をおこなって下さい。電話対応は、被災地の大きな負担に繋がりかねません。しかし、専用のコールセンターを立ち上げてる場合、そこに連絡を取るのが良い場合もあるので、状況にあった判断を取る事が大切です。
上記の『適した服装・装備・適した物・備品』の一覧を作りました。荷物を持って行く時の『チェックシート』として使えます。(※無断配布・二次使用等禁止)
英語のチェックシート内で、翻訳や言葉が間違っている場合、教えて頂けたたら確認後、適宜修正をします。
ここまでは、ボランティア活動の『作業をおこっている時』に必要な服装や物について紹介をしました。備品の項目は、ボランティア活動に参加する場所によっては『必要であったり、必要のない物もある』ので、持参する物は、十分な検討をして下さい。ここに書いた物の殆どは、ホームセンターや、通販サイトで手に入れる事ができます。
持って行く物は『軽く・最小限』にしたいと考えると思いますが、被災地の方に迷惑や負担をかけない為には『十分な装備』で行く事に注力して下さい。
ボランティア開始までの流れ
被災地の現場に行き『ボランティア活動』の作業に入る前に、いくつか行う事があります。
受付
ボランティアの活動を行う被災地に到着をしたら、ボランティアセンターで『氏名・住所・ボランティア活動経験の有無・ボランティア保険加入の有無』などで受付(登録)をおこないます。
オリエンテーション
担当の方から『作業内容・自分の役割・注意点』などの話しがあります。
マッチング
被災地の現場から『要望』がある場合、その要望に沿い、作業をおこないます。場合によっては、待機時間などもあります。
受け取り
必要な資材などを『資材受け渡し場所』から受け取ります。
活動の開始
上記の内容が終わると『ボランティアの作業』に入ります。活動中『お互いの協力』や『情報の共有』が大切になります。声を掛け合い『無事故』で作業を進めて下さい。当たり前の事ですが、これが『何よりも1番大切な事』です。

ボランティア活動の終了
うがい・手洗い・道具の洗浄
自身の泥や汚れを落として下さい。ホコリや泥などからの細菌感染防止の為にも必須です。併せて、使用した道具や借りた物も、洗浄し返却をして下さい。自分を守るのは、他の誰でもありません『自分自身』です。
作業の報告
最初に受付(登録)をしたボランティアセンターへ、おこなった作業の報告をします。作業の終わった部分や、終わらなかった部分、あるいは、新たな支援が必要になった場合なども報告をします。
解散・帰路
ここまでの内容が、全て滞りなく終了したら、速やかに『自宅』へ向かうか、あるいは『宿泊先』に戻ります。続けて次の日も、ボランティアに参加をする場合は、十分に疲れを取る事が大切です。
また、ボランティア活動は、力仕事だけではありません。
しばらくの間、1番多く人数が必要なのは、家などからの泥出しや荷物運びの作業です。家から外に運び出した物は、児童の通学路の道など、両脇2~3mの壁になり積まれている場所も多くあります。それを『処分場』へ、軽トラックなどを運転して、運搬する人の人数も、圧倒的に足りてないようです。
他にも『消毒・支援物資の仕分け・送迎』や、あるいは『専門職の方の知識と経験』などが必要な場面もあります。全国からの支援物資も多くありますが、その真心の品々の仕分けをするのも、かなりの労力が必要で、作業は直ぐには終わりません。自分が出来る事を手伝うのが1番です。
支援物資を『送る側』も、被災地の『届いた側』の事を考えた時、段ボールの外からでも、中に何が入っているかが分かる工夫をすると、仕分けをおこなう前から、ある程度置く場所を決められるので、作業効率が上がり、負担が減ります。引越しをした事のある方なら、その工夫を経験しているかも知れません。
被災地では『電気・水道・ガス』のインフラが復旧をしていない場所もあり、食料が十分に届かない場所もあります。先述したように『自分の事は、自分で責任を持つ』事が大前提です。昼食など、自分の食料をどうするかを、ボランティアに入る現場の状況などを十分に確認し、準備を整えて下さい。
持ち物の管理も自己責任です。紛失・盗難に合わないように自己管理をして下さい。
また、被災地には、大量に物が積み重なり、使用できないものが、数多くあります。しかし、それらの全ては『被災した方々の思い出の品々』です。二度と手に入れる事の出来ない物や、思い出の品なども、積まれています。作業を手伝う時にも『ゴミ』として表現するのではなく『被災者の方の気持ちを考え・行動する事が最重要』です。
例えば、泥まみれになり、自分には必要ない物に見えても、その家の方には、捨てられない大切な物も、数多くあります。『手伝って欲しい事・そのままにしておいて欲しい事』もあるので、ゆっくり・丁寧に、被災者の方の気持ちに寄り添い、声をかけ、確認しながら作業を進める事が大切です。
併せて『写真撮影には十分注意』をして下さい。被災された方が『自分の家の中』などを写真や動画で撮影され、世界に発信・公開された時、どんな気持ちになるかを考えてみて下さい。あなた自身が『自分の家の中の写真などを公開されたら』何を感じるでしょうか?被災された方の気持ちを考えず、不用意に撮影や『SNS』などに公開をしないように注意が必要です。
複数日、被災地に入ろうと思っている方は、自分の『宿泊先』を確保しなければなりません。被災地に近い場所では、ホテルなどでも『電気・ガス・水道』のインフラが、止まっている場所もあるかも知れません。
また、泊りでボランティアをおこなう場合、しっかりと疲れが取れない為『車中泊』や『テント』や『寝袋』は、出来るだけ避けたい手段です。自分が我慢をすれば良い!と思っても、次の日に、想像以上に大変な作業をおこない、自分が倒れて『被災者の方に心配や迷惑をかけない』よう、十分な注意が必要です。水分や休憩をためらわず取り、自分の体を守りながら作業を進める事が肝心です。
被災地から少し離れた場所などで『宿泊先』を見つけた場合、そこからの被災地に行く『交通手段』も調べなければなりません。もちろん交通費や宿泊代なども『全額自己負担』です。途中、道路が寸断され、行く事が困難な場所も予想されます。
車で行くと、被災地の迷惑になる場合もあるので、行く場合は『公共交通機関』を利用しての移動が大切です。場合によっては、徒歩の部分もあるかも知れません。東日本大震災の時は『ガソリン』などの燃料の入手も大変な地域も多くありました。

災害派遣等従事車両
先述したように、車を運転する方の人数も足りない地域があるようです。今回の『平成30年7月豪雨』の災害援助などを目的とする車両に対して『災害派遣等従事車両証明書』の交付を受ける事ができます。
これは、高速道路などの有料道路の料金所を通る際、本証明書を提出する事によって『有料道路の通行料が無料』になる証明書の発行ができるものです。
この証明書は、災害時における、救急車などの『優先通行車両』になるものではありません。あくまでも『有料道路の料金について、無料の措置を講じる』ものです。
この『災害派遣等従事車両証明書』の発行には数日必要です。また『証明書発行の対象期間があり』効果のある有料道路なども、ボランティア活動に参加する地域によって変わります。
詳しくは下記、各府県の『災害派遣等従事車両証明書』の説明サイトなどで確認をおこなって下さい。証明書は『郵送』などでは発行されず『窓口で申請・受け取り』をおこないます。各市区町村でも発行している場所があるので『役所』のホームページなどで確認をしてみて下さい。(表が大きい時、横に動きます)
ボランティア活動向けの割引
今は広島県など、道路が寸断され陸路での移動が困難な場所などでは、海路から被災地に行く『フェリー』の運行などが積極的にされています。被災地に行く1つの手段となります。
また、下記の割引には『販売期間』や『有効地域』が限定されるので、利用する際は、十分な確認をおこなって下さい。(表が大きい場合、右に動きます)
| 発行元 | 割引の案内サイト |
| 国土交通省 | フェリー割引運賃の実施 |
| JR西日本 | こだま限定自由席片道きっぷの販売について |
また、ボランティア活動が一区切りすると、別の手伝える事も出てきます。
例えば『足湯を用意し、マッサージなどで疲れを癒したり』あるいは『炊き出し』をおこなったり、あるいは、お年寄りなどの話しを聞く『傾聴』などの活動も必要になるかも知れません。
ボランティア活動は『肉体的にも・精神的にも・想像以上に大変』な場合が多くあります。自分の作業が終わり、家に帰る前に、観光地やショッピングセンターなどで『気分転換をし、気持ちを落ち着かせ、クールダウンをおこなってから帰るのも、自分の心や体を守る為にも、自己管理として大切』になります。時間や体力に余裕があれば、おこなってみて下さい。
最後に付け加えるとしたら、被災地の現場に行き作業をするだけが『ボランティア活動』ではありません。『家から支援物資を送ったり』あるいは『支援金を送金したり』と、現地に行かずとも、出来る事はあります。まずは『行動を起こす』事が大切です。『真心を持って、自分には何が出来るのかを考え、ボランティア活動に参加する事が、何よりも大切な事』だと思います。
全社協 被災地支援・災害ボランティア情報の『ボランティアのみなさまへ』には、ボランティア活動に必要な情報を公開しているので、参考にしてみて下さい。
ボランティア活動保険
万が一の時の為に『ボランティア活動保険』への加入をしておくと安心に繋がります。保険を申し込む場合、基本的に『居住地(現住所)』の『社会福祉協議会』で加入が出来るので、被災地へ向かう前に手続きを完了して下さい。
保険自体の加入は任意ですが、ボランティアセンターによっては、加入を『必須』としている地域もあります。ご自身が参加をしようとするボランティアセンターの状況を確認の上、保険の加入の検討をして下さい。
尚、自治体などのホームページ内に書かれている『保険』の内容が古い情報のままになっている場合があります。最新の『ボランティア活動保険』の内容は『ふくしの保険』や『社会福祉協議会の窓口』で、確認をおこなって下さい。
全国社会福祉協議会の一覧は『都道府県・指定都市社会福祉協議会ホームページ』あります。
『ボランティア活動保険』には
『基本タイプ』と『天災タイプ』があります。
基本タイプ
ボランティア活動中の『ケガと損害賠償責任を補償するタイプ』ですが『地震・噴火・津波』による天災では、ケガは補償されません。
天災タイプ
基本タイプの補償範囲に加えて、天災の『地震・噴火・津波』による被保険者(ご自身)のケガも補償するプランです。
『基本タイプ』と『天災タイプ』それぞれに『Aタイプ』と『Bタイプ』があります。
『Aタイプ』と『Bタイプ』では保険料が異なり、補償の金額が変わってきます。(※表は右に動きます。下記料金は、平成30年度の保険料)
| Aタイプ | Bタイプ | |
| 基本タイプ | 350円 | 510円 |
| 天災タイプ (基本タイプ+地震・噴火・津波) | 500円 | 710円 |
保険料や補償については『ふくしの保険』の『ボランティア活動保険』で、必ず確認をして下さい。
『ボランティア活動保険』は、平成30年度加入申込み分から『送迎サービス利用時の事故』は保険適用外になり、補償が必要な時は、新たに『送迎サービス保障』の保険への加入が必要になっています。各保険内容が、去年までと変わる部分があるようなので、加入前に保険内容などをよく確認し、検討をおこなって下さい。
また『加入申込書の2枚目』に、社会福祉協議会の確認印が捺印された用紙が『加入証』になります。ボランティア活動の申し込みをおこなう際、必要になる事もあるので、大切に保管をして下さい。
『ボランティア活動保険』は『ふくしの保険』に、詳しく書かれています。
支援金と義援金
ここからは『支援金』や『義援金』を受け付けている団体などを紹介します。
よく目にする『支援金』と『義援金』ですが、被災地や、被災者の方の手助けになる『お金』という意味では同じですが、実は内容が大きく異なるので、最初に、その違いから紹介したいと思います。
『支援金と義援金』の違い
支援金
まずは『支援金』についてです。支援金は、自分が応援したい団体や、関心のある分野の団体を選び、被災地の支援に役立てて貰うお金です。
お金の使い道は
自分が選んで寄付する『各機関やNPO・ボランティア団体』などの『判断と責任』において『柔軟』に使用されます。
これは被災地からの『要望』に対し、その団体の『判断』で『お金』を使用できるので、活用までの時間が早いのが特徴です。使用目的は主に『人命救助や道路などのインフラ整備』などに使われます。また、各団体ごとに支援金の使途や収支の報告をおこない透明性を保っています。
義援金
次に『義援金』についてです。義援金は、被災者の方々へ、お悔やみや応援の気持ちを込めて贈るお金です。主な団体として『日本赤十字社・赤い羽根共同募金・自治体・テレビ局』などが受付をおこなっています。
お金の使い道は
被災した県や府が設置した『義援金配分委員会』によって、寄付された『お金の100%が被災者の方へ、公平・平等に分配』されます。その為、ボランティア団体や、行政がおこなう復興事業や緊急支援には使用されません。
例えば『日本赤十字社』に寄付されたお金は、県や府が設置した『義援金配分委員会』に送金され、そこから『管下』の市区町村に『義援金』が送金されます。更に『被災者の方』からの申請に基づき、市区町村から『義援金』が被災者の方へ届けられます。
また、集まった寄付金は、均等に配分をする為、被災者数などの正確な情報の確認後になるので『配分までに時間を必要とし、その作業は被災した自治体がおこなう』ため、負担が大きいのも特徴です。
『支援金』と『義援金』の内容を『表』にすると、それぞれの特徴が分かり易くなります。(※大きい場合、右に動きます)
| 支援金 | 義援金 | |
| 使用目的 | 人命救助・インフラ整備など | 被災者へ公平・平等に配分 |
| 責任や利用方法 | 団体などに一任 | 自治体が被災者へ均等配分 |
| 届くまでの時間 | 迅速 | 情報確認後の為、遅い |
それぞれに特徴があるので、ご自身の希望に合った、これらの内容などを理解した上での『寄付』が大切です。
また『支援金』を扱う団体は、その団体に使用方法が任されています。全く聞いた事のない団体や『使途不明』あるいは『収支報告』のない団体への『寄付』は、十分な確認をおこない注意して下さい。
寄付を受け付けている団体
それぞれ『振込先』や『受付期間』があるので確認が必要です。(大きい場合、表は右に動きます)
| 団体名 | 寄付金募集の案内があるページ |
| 日本赤十字社 | 平成30年7月豪雨災害義援金 |
| 赤い羽根共同募金 | 平成30年7月豪雨災害 |
| 日本財団 | 災害復興支援特別基金・平成30年7月豪雨 |
| Yahoo!基金 | 平成30年7月豪雨緊急災害支援募金 |
| 楽天クラッチ募金 | 平成30年7月西日本豪雨被害支援募金 |
| LINE 公式ブログ | 平成30年7月豪雨災害の被災者支援への寄付を受付開始しました |
| ふるさとチョイス | 平成30年7月豪雨 |
| みんなでつくる財団おかやま | ももたろう基金 |
| 岡山県 | 平成30年7月豪雨岡山県災害義援金の受付を行っています |
| 愛媛県 | 平成30年7月豪雨災害に係る義援金の募集について |
| 神戸市社会福祉協議会 | 平成30年7月豪雨災害緊急救援募金 (平成30年9月30日まで) |
| Organization name / Official website | |
| Japanese Red Cross Society | |
| Red feather cosponsor | |
英語で書いてあるページは、上記団体で英語のページが用意されている場合紹介をしています。寄付金を募集している団体は、この他にも数多くあります。
例えば、フジテレビ系列がおこなっている『フジネットワークサザエさん募金』は、集まったお金を『日本赤十字社』に送金します。このような場合、必然的に『募集期間』は『日本赤十字社』の募集期間より早く終了をします。

注意書き・免責
今回紹介した情報の全ては、十分な確認をおこない掲載していますが、間違っている部分や、古い情報が混ざっている場合があるかも知れません。必要な情報は関連の『公式ホームページ』などで、十分に確認をおこなって下さい。
上記にある『寄付金を受け付けている団体』で紹介しているものは、当サイトの性質上『募集期間』が終了しても、一覧に掲載されて残ります。
当サイトや管理人は『当サイトに掲載されている情報』や『リンク先のサイト』などについて、一切の問題や責任や賠償などを負いかねます。